財政の健全化は難しいですね
国の財政は歳入(収入)と歳出(支出)で成立しているのはご存じの通りだと思います。これについて分析していきます。
歳出部門
平成27年度(2015年度)歳出部門で32.7%と多くを占めているのは、は31兆5,297 億円で社会保障関連費です。中でも35.2%を占めているのが、年金です。年金は賦課方式で開始されましたが、昨今の少子高齢化によってそれ単独で行うことができないようになりました。従って大量に税金を投入することによってなんとか補っているような状況です。私がお爺さんになる事には満足に貰うことができるのでしょうか。
厚生労働委員会調査室 吉成 俊治 「平成 27 年度(2015 年度)社会保障関係予算 ― 社会保障に対する信頼と制度の持続可能性 」の図解より抜粋
かといってこの税金を抑えなければ、財政の健全化を見ざすことはできません。しかし、それも難しいです。理由としては日本の有権者の殆どが高齢者となってしまっているからです。いわば世代間の一票の格差と呼ばれる状況で、表の重さが変わってしまうことから偏った政治が行われやすい政治体制になってしまっています。今回の場合高齢者に偏っているため、シルバー民主主義と言われたりしますね。個人的には政治は長期的に物事を考える場だと考えているので、若年層により強い力を与えるべきだと思います。選挙権にも定年を設けるか、世代間別投票、子供選挙代理権制度を設けるべきでしょう。
少子高齢化の進行で有権者に占める高齢者(シルバー)の割合が増し、高齢者層の政治への影響力が増大する現象。
コトバンク「シルバー民主主義」より引用
歳入部門
歳入部門が一番やりやすいのではないかと思います。原則として増税は国民の生活に負担がかかることから、国民はもちろん反対します。しかし、目的化した負担は受け入れてくれるケースが多いです。例えば電源開発促進税法という電力供給の円滑化の為に作られた増税であったり、安倍総理が消費税を増税することが明らかになり、反対も多かったですが、後に増税の際教育の無償化に使うと表明した瞬間歓迎ムードになりました。税金ではないですが、原発を停止したことで再生可能エネルギーに力を入れていこうということで、再生可能エネルギー発電促進賦課金という制度を設け、固定買取制度を始めたわけですが、このおかげで電気料金は10%以上値上がりしています。が、見事に受け入れられています。
東京電力「賦課金等について」 興味がある方は参考に

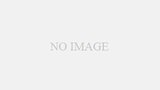
コメント