長嶋一茂「筋肉を使わないモノはスポーツを名乗るな」と発言したことで、炎上していますね。私も実は雑魚ですがゲーマーで、最近だとゴットイーター3を楽しくプレイしています(笑)
結論から先に言いましょう。eスポーツはスポーツであって、スポーツではありません。なぜならば現在は言葉の意味の転換点(再定義点)にいる為です。
ですから長島さんが「筋肉を使わないものはスポーツではない」と言うのも正解ですし、私たちゲーマーが「eスポーツはスポーツだ」と感じるのも正解です。炎上させる必要などありません。至極真っ当な意見ですよ。
いつもであれば20時更新でしたが、話題性の高いもの&不必要な炎上から個人を守る必要があると判断して投稿しました。
e-スポーツとは
eスポーツというのはエレクトロニック・スポーツ(electronic sports)の略称です。数あるゲームソフトの中で、e-スポーツの対象になるのは複数のプレイヤーで対戦するゲーム。従ってギャルゲー等は含まれないことになります。
実は歴史上「筋肉の使わないスポーツが実在していた」
あくまでもWikipediaからの引用になりますが、17世紀~18世紀においては、競馬やディベート、歌劇や合奏、カードゲームがスポーツに含まれていたようですね。
しかし、19世紀になって、スポーツとは運動競技であると意味が変わったようです。
その原義は現在も保持されているが、意味するものは時代とともに多様化している。17世紀 – 18世紀には、sportは伝統的貴族や新興階級の地主ジェントリの特権的遊びである狐狩り等の狩猟を筆頭に、競馬やディベート(弁論)、歌劇や合奏の競演、カードゲームや盤ゲームなど多岐にわたった。
しかし19世紀に入ると、権威主義に対抗した筋肉的キリスト教 (en:Muscular Christianity) 運動や、運動競技による人格形成論が台頭、貴族階級から開放され労働階級によるスポーツの大衆化が進んだ。近代になると統括組織(競技連盟など)によって整備されたルールに則って運営され、試合結果を記録として比較し、娯楽性よりも記録の更新をよしとする競技を第一に意味するようになった。日本でも国民の身体的健康を目的として運動競技=スポーツを推奨し、現在まで定着した。
Wikipedia「スポーツ」より引用と強調
現在は言葉の意味の転換点(再定義点)にある
スポーツから「筋肉を使わないもの」が排除されたように、今は新たにそれを認めていくべきではないかという運動が始まってきた兆しでしょう。
言葉というのは、変化していくものです。
例えば、割愛しますという言葉。皆さんは、「不必要なことを省略する」という意味合いで使っていると思いますが、実の意味は、「惜しいと思うものを手放す」という意味です。しかし、多くの人が「不必要なことを省略する」という言葉で使っていますし言語学者も認めるような流れになってきています。
そういった意味でスポーツも言葉の意味の転換点(再定義点)に置かれていると解釈するのが妥当でしょう。なので長嶋一茂さんの発言も間違っているものではありません。
どちらが多数派になるのか勝負の始まりですね。
個人的にはeスポーツはスポーツと認めるべき
そもそも、日本だけではなく、世界において、ゲームで遊んでいる人=犯罪者であるかのような報道がされていることはみなさんもご存知の事だと思います。しかし、仮にスポーツとして認めてもらえれば、社会的地位が尊重されるのではないかと思っています。
更にゲームが好きでない人にも朗報があります。eスポーツがスポーツとして認められれば、大会等が各地で行われることになります。つまり観光客が増加するのです。
観光客が増加すれば、インバウンド消費が望めることになり、経済が活性化します。認めて得することはあっても損することはないんだから、認めてもいいのではないかと私は思います。
ましてや日本には「任天堂」「SONY」「遊戯王」という世界に誇るゲームブランドがあり、そちらの販売促進にもつながりますよ(笑)

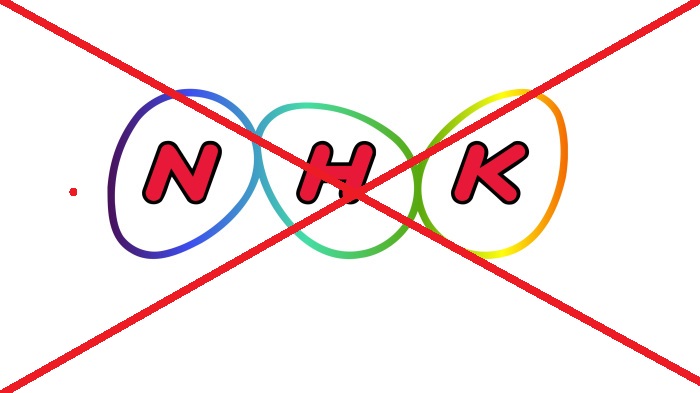

コメント